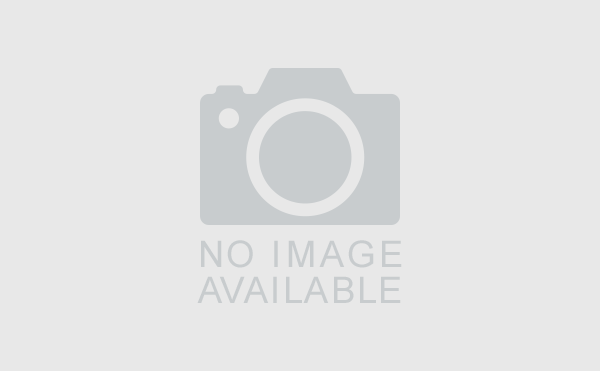郵券
「郵券(ゆうけん)」とは郵便切手のことです。
耳で「ゆうけん」と聞いても何のことかよく分かりませんが漢字を見れば何となく想像できますね。
民事訴訟を提起するときに,裁判所にあらかじめ納める郵便切手を「予納郵券(よのうゆうけん)」といいます。
裁判所は,この予納郵券を使って訴状や呼出状,判決などの書類を送付します。
事件が終了した時点で,余った(使わなかった)郵券は返還されます。
予納郵券の内訳(いくらの切手を何枚ずつという組み合わせ)は裁判所や事件によって様々なので,訴訟を提起する前に裁判所に確認するのが確実です。弁護士も,裁判の種類や裁判所によっては,訴訟提起前に裁判所へ電話して確認しています。
裁判所内の売店や郵便局では,セットにした郵券も販売しています。
最近は,郵券を現金で納付できる(郵券の金額(郵便料)に相当する現金を納付して,事件終了時に余った金額を現金で返してもらう)裁判所も増えてきましたが,できない裁判所もまだあります。
また、少し前から電子納付という方法で郵便料を納付できる制度も始まっています。
これは、保管金提出書という書類をもらって、それに記載されている情報をもとにインターネットバンキングなどで郵便料などを納付できる制度です。ただし、利用者登録が必要なので、弁護士はともかく、一般の方が利用するには少しハードルが高いかもしれません。
福岡だと福岡地方裁判所では郵便料の電子納付が可能ですが,福岡簡易裁判所ではまだできないようです。
(2021年2月時点)
2025年1月6日から、全国の家庭裁判所、簡易裁判所でも電子納付ができるようになりました。
2026年にはオンライン申立て、それに伴う申立手数料の電子納付も始まりそうです。
(現在は、申立手数料は収入印紙で納付しています。)
裁判手続の申立ても随分と様変わりしていきそうです。
福岡家庭裁判所への申立てで電子納付を希望したのですが、相手方への送付が必要なのでという理由で郵券を納付してくださいと言われました。
したがって、いまの時点では、家庭裁判所で電子納付をする意味はなさそうです。
(2025年4月時点)
弁護士の場合は,返還された郵券を使い回しすることも可能ですが,一般の方が自分で裁判を起こした場合には,現金納付ができないと,事件終了時に通常は使わない金額の郵券を何枚も返されるということもあり,使い道がなくて困ってしまいますよね。